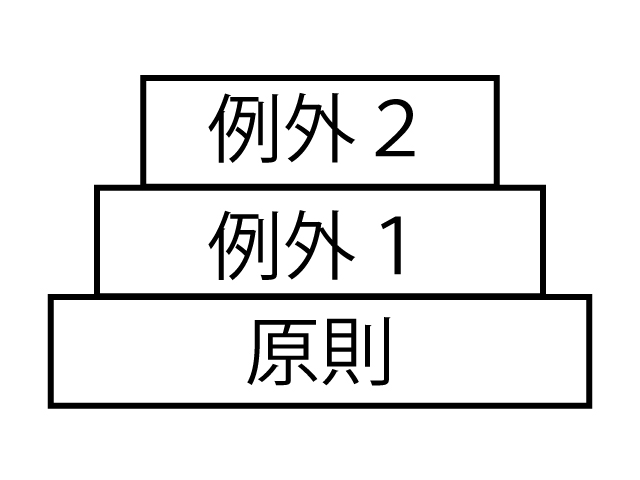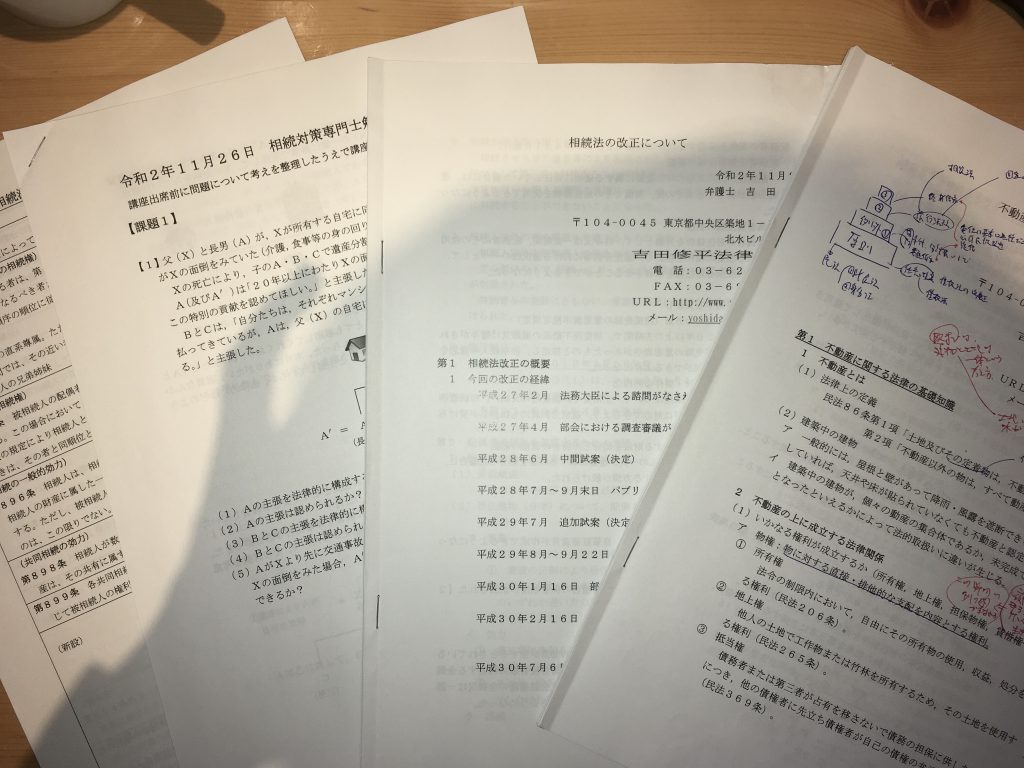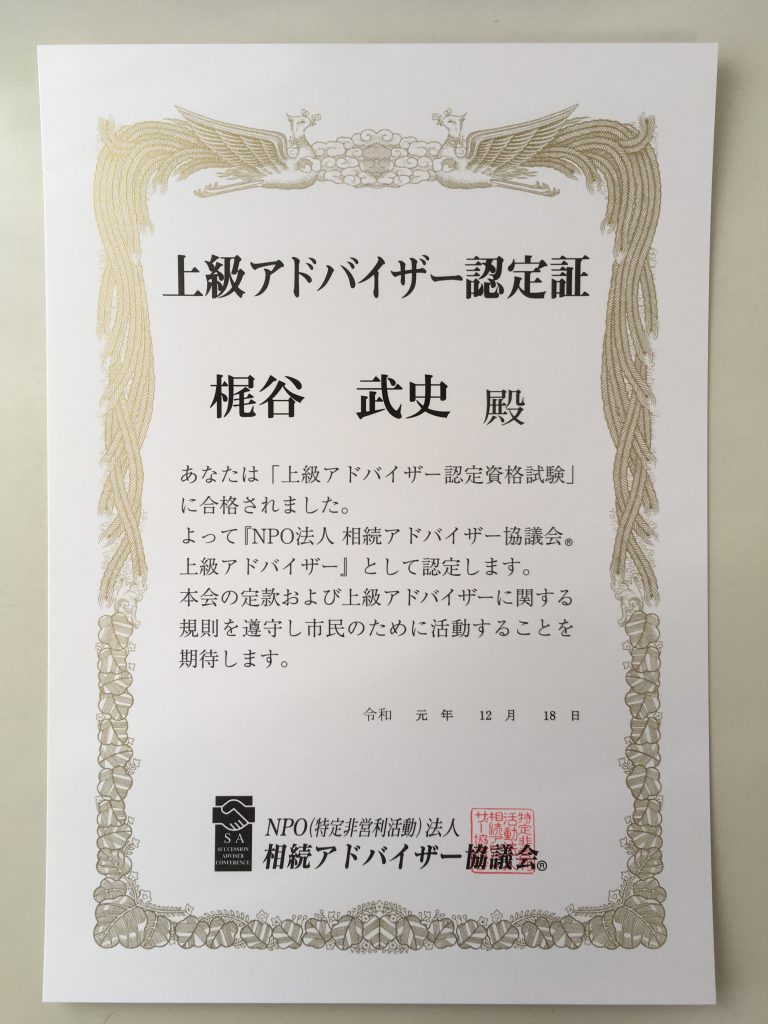昨日に引き続き、相続法改正についてお伝えします。
昨年2019年7月1日施行の
相続法(民法)の改正で、遺留分制度に関する見直しがありました。
相続においては様々な家族関係や各種事情があるとは思いますが、今回の遺留分制度の見直しについては、特に中小企業の事業承継において大きなメリットが出てくるものと思われます。
1.遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人について、被相続人の財産の一定割合の相続権を保証する制度になります。
この遺留分を保証すれば、被相続人は遺言によって、残りの財産を自由に処分することができます。
兄弟姉妹以外の法定相続人である、配偶者、子、直系尊属には遺留分があります。
例えば、妻と子供が相続人の場合は、遺留分は法定相続分の2分の1となります。
また、相続廃除や相続放棄などによって相続権を失った場合には、遺留分権も失うことになります。
2.改正前の制度(遺留分減殺請求権)
改正前までの制度では、
遺留分権利者が、被相続人が遺留分を侵害するような遺贈や生前贈与をしたとき、
遺留分権利者が遺留分減殺請求を行使すると、当然に物権的効果が生じて遺贈などが無効となるため、対象物は受遺者等と相続人との共有になりました。
そのため、その後、共有物の分割を行う必要があり、場合によっては共有物分割訴訟の手続きを地方裁判所で取る必要が出てきます。
例えば、被相続人である父親と、相続人である3人の息子がいたとします。
父親は、商売の後継ぎとして一緒に働いていた長男に対して、会社の株式や事務所や店舗、工場などの不動産を生前に贈与していたとします。
しかし、父親の死後、次男と三男がそれに対して遺留分を請求したとします。
この場合、次男と三男の遺留分は、法定相続分である3分の1の2分の1である各6分の1となります。
すると、父親から長男へ生前贈与されていた会社の株と不動産は、当然に物権的効力が生じて、次のようになります。
まず、不動産は、
長男6分の4、次男6分の1、三男6分の1の
共有となります。
そして株は、
長男6分の4、次男6分の1、三男6分の1
の準共有になります。
しかも、株の場合は、一株単位で準共有となるため、議決権行使をする度に、3人で話し合いをする必要が出てきます。
これでは、受遺者が中小企業等の後継者である場合には、事務所や店舗、工場などの会社の資産や自社株式などを単独で所有することができずに共有となるため様々な制約が出てきてしまい、円滑な事業承継も困難になってしまいます。
3.改正後の制度(遺留分侵害額請求権)
そこで、改正後の制度においては、
遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができること、とされました。
つまり、金銭債券化されることになりました。
それによって、不動産や会社の株式などの対象物は、受遺者や受贈者などの単独所有となりました。
先の例でいうと、
父親が後継ぎの長男に対して、自社株3億円と、事業用の不動産3億円を生前に贈与していたとします。
その場合、次男と三男の遺留分は、各6分の1となります。
父親が他界して、次男と三男が遺留分侵害額請求を行使した場合、
次男と三男は、長男に対して、計6億円の6分の1である1億円づつを支払うように請求できるようになります。
つまり、生前贈与された自社株と不動産は長男の単独所有となり、長男は次男と三男に各1億円の金銭債務を負うことになりました。
なお、受遺者または受贈者の請求により、裁判所は金銭債務の支払いについて、相当の期限を許容することができます。
4.改正の影響
改正前より、遺留分権利者の多くは、受遺者などから金銭を支払ってもらうことによって解決することを望んでいましたが、このことが法的な面からも正式に認められるようになりました。
さらに、改正前の制度では、物権的効果によって共有物の分割を行う必要が生じていましたが、共有物の分割は時間やお金もかかるため、実用的ではありませんでした。
このことを回避できることは、とても大きな意義があるものと思われます。
また、繰り返しになりますが、受遺者や受贈者が中小企業などの後継者の場合においては、事務所や店舗、工場などの会社の資産や、自社の株式などが単独で所有することができるようになったため、改正前のような共有による制約が解消され、先代から後継者への事業承継の手続きがやり易くなるもと思われます。